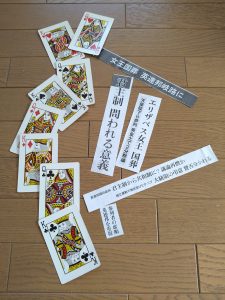今週の書物/
朝日新聞写真館since1904「週刊朝日『ジャンプ’63』上・下」
朝日新聞2023年5月27日付夕刊、同年6月3日付夕刊

先週に続けて今週も、当欄は特別番組を組む。2週連続で本から離れるというのは心苦しいが、今を逃すとタイミングを失するので決行させていただこう。
バタバタした理由は、私のうっかりにある。「週刊朝日」の休刊についてはすでに書いているが(*1)、最終号が5月30日に出たら、それも読み、改めて話題にしようというのが私の構想だった。ただ30日から2日間、温泉旅行の予定があった。最終号は旅先でも買えるだろうと高を括っていたが、最近は週刊誌を置く駅の売店がなかなか見つからない。31日に東京に戻り、わが町の昔ながらの書店に駆け込むと、もう売り切れだった。
部数が減ったことで、休刊に追い込まれる。ところが最終号が店頭に並ぶと、飛ぶように売れる。なんとも皮肉な話だ。とまれ、私の計画は泡と消えた。
そんなときだ。古新聞の切り抜きをしていて、おもしろい記事に出あった。土曜日夕刊に「朝日新聞写真館since1904」という連載があるのだが、5月27日と6月3日に上下2回で「週刊朝日『ジャンプ’63』」と題する写真特集が掲載されていた。新聞が届いた日にはうっかり見逃したが、後日切り抜き作業で目にとまり、被写体となった人物たちのポーズに思わず見とれてしまったというわけだ。だれもかれも、無邪気に跳んでいるではないか。
「ジャンプ’63」は、「週刊朝日」1963年の新年企画。「編集部の要請で各界のスターら約100人が次々跳ね、新年から3号にわたってグラビア誌面を埋めた」(「写真館」下の回の前文記事)ということらしい。「写真館」では、上下9人ずつ計18人が登場する。芸術家がいる、俳優がいる、映画監督がいる、経営者もいる、そして政治家も……。アトリエで跳んだり、稽古場や撮影所で跳ねたり、自宅応接間でジャンプしたり……。
私が思わずうなったのは、当時の「週刊朝日」が押さえるべきところを押さえていたことだ。1963年年頭の時点で、的確な先物買いをしている。たとえば政界では、1964年から8年間の長期政権を担った衆議院議員の佐藤栄作がいる。文化の領域では、1970年の大阪万博で「太陽の塔」をデザインした前衛芸術家の岡本太郎がいる。2023年の現在に至るまで国民的スターであり続けている女優の吉永小百合もいる。(敬称略、以下も)
もちろん、今回の「写真館」上下2回では約100人を18人に絞っているわけだから、歴史に名を刻んだ人物が選ばれているということはあるだろう。それにしても、である。
佐藤栄作は1963年、すでに有力政治家で閣僚経験も豊富だったが、63年年頭に限れば一代議士に過ぎなかった。当時の首相は池田勇人で、自民党内では官僚出身の佐藤と党人派の河野一郎が跡目を争うライバルだったが、大衆の人気だけでいえば河野に分があったように思う。もしかすると、この企画では河野にも跳んでもらっているのかもしれない。ただ、佐藤に声をかけることを忘れなかった。抜け目のない判断といえるだろう。
佐藤の跳び姿を見てみよう。両手を挙げ、スーツ姿で跳びあがっている。撮影場所は自宅応接間。背後にドアがあり、床には絨毯が敷かれているようだが、全体として質素な印象を受ける。驚くのは、佐藤が革靴を履いていることだ。この部屋は、靴を脱がない欧米式なのか。いかにもだな、と思わせるのは、こんなときでもワイシャツの袖口がカフスボタンで留められていることだ。一分の隙もない感じ。人気が出ないのももっともだ。
このとき佐藤は61歳。ジャンプ力はなかなかのもので、両手はほとんど天井に届いている。そのポーズを見て、私は51年前のバンザイを思いだした。1972年、沖縄復帰記念式典で佐藤首相は「日本国万歳、天皇陛下万歳」と発声し、会場は万歳三唱に包まれた。変な気分だった。日本は高度経済成長を果たし、戦争の傷跡を忘れかけている。ところが、それとは逆に自由の空気はしぼんでいる。その中心にいたのが佐藤首相だった。
「ジャンプ’63」の顔ぶれは、いずれも時代を映しだしている。松下電器産業会長の松下幸之助は自社の会長室で、拳を握りしめ、右手を高々と挙げて跳んでいる。1960年代前半といえば、電化製品が去年はあれ、今年はこれ、というように家庭になだれ込んだ時期に当たる。家電を買えるだけの給与増があったという意味でも、家事労働が軽減されたという意味でも、豊かさを実感できる時代だった。松下の跳び姿には、その勢いがある。
俳優の三船敏郎は海老反りで豪快なジャンプだ。三船といえば、疲労回復薬やビールのCMが猛烈サラリーマンの心をつかんだ。高度成長を象徴する人物だったといえよう。
ただ、高度成長期は猛烈だったが、優しい一面もあった。あのころの大人は戦争が人間性を毀損する記憶から逃れられず、ヒューマニズムを渇望していたのではないか。シナリオ作家松山善三と俳優高峰秀子夫妻が自宅で仲良く跳ぶ姿を見ると、そんなふうに思える。
これらの写真群のなかで、もっともジャンプに似合わない人は、映画監督の小津安二郎だろう。和服をキリっと着こなして自宅の客間で跳んでいるのだが、小津映画風のローアングルで見あげても、爪先は床の間の段差ほども上がっていない。それはそうだ。小津はこのときまでに代表作のほとんどを撮り終えていたからだ。このころは、すでに静かな境地にあったのではないか。それ以降に飛躍したのは、小津の世界的な名声だった。
作家有吉佐和子も和室で着物姿。当時すでに『紀ノ川』などの作品で人気作家だったが、1970年代に入ると果敢に社会問題に挑んだ。『恍惚の人』、そして『複合汚染』。ジャーナリスティックなテーマを次々見つけ、飛び石を渡るようにぴょんぴょん跳んでいった。
俳優森光子は、和服姿で膝を曲げ、数十センチも跳びあがっている。森といえば舞台でのでんぐり返しが有名だが、その素養は若いころからあったのだ。俳優岡田茉莉子はシックな洋装で、体操選手のように跳んでいる。この人は1970年、夫吉田喜重監督の「エロス+虐殺」でアナーキストの愛人になった(*2)。2時間ドラマの人気シリーズ「温泉若おかみの殺人推理」では憎めない大おかみも演じている……半世紀余の記憶が脳裏を駆けめぐる。
「ジャンプ’63」で懐かしさを覚えるのは、評論家大宅壮一のいでたち。「写真館」登場の18人で男性の和服姿は小津と大宅の二人きりだが、小津のキリッに対して大宅はグダッ。おとうさんが勤めから帰って、夕飯のために着物に着かえたという感じだ。あのころは、そんなおとうさんがどこにもいた。大宅は、書物がぎっしり並ぶ自宅書庫の書棚に挟まれた空間で、結構な高さまで跳んでいる。ジャーナリズムが元気な時代ではあった。
考えてみれば、1963年は、戦後日本がもっとも明るさに満ちていたころだった。その時代精神を「ジャンプ」という動作で可視化した「週刊朝日」編集部には脱帽だ。「跳んでください」と言われた人々もまんざらではなかったのだろう。思いっきり跳べば高みに手が届くはず、という期待があのころはみんなにあった。各界で活躍する人たちなら、その期待は確信に近かったに違いない。だから、みんなうれしそうに跳んでくれたのだ。
いま痛感するのは、「週刊朝日」の過去号(バックナンバー)は私たちにとってかけがえのない財産である、ということだ。そこにあるのは、新聞の縮刷版が具えた記録性と同じものではない。雑誌の過去号には、その号が出た時代の空気が詰まっている。雑誌は、いわば街角。過去号があればタイムマシンにでも乗るようにあのころの街角に戻り、あのころの空気を吸える。雑誌のアーカイブズを大事にしなくてはならない、とつくづく思う。
*1 当欄2023年2月17日付「『週刊朝日』デキゴトの見方」
*2 当欄2023年3月24日付「竹中労が大杉栄で吠える話」
(執筆撮影・尾関章)
=2023年6月16日公開、通算682回
■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。
■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。
■公開後の更新は最小限にとどめます。
-scaled-1.jpg)