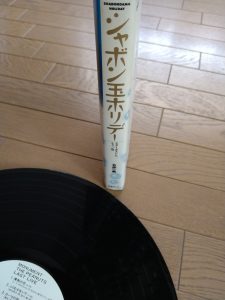今週の書物/
『東京懐かし写真帖』
秋山武雄著、読売新聞都内版編集室編、中公新書ラクレ、2019年刊

水害が頻発している。最近は、その怖さがすぐニュース映像になる。たとえば、濁流が家々を押し流す場面。住人はすでに現場から避難していると聞いても気がかりはある。一瞬、頭をよぎるのは、家を出るときにアルバムを持ちだせただろうか、ということだ。
アルバムに対する思いは、高齢の人ほど強い。写真が画像データとは呼ばれなかった時代、それをUSBメモリーやSDカードに保存したり、ネットの雲(クラウド)に載っけたりはできなかった。だから、紙焼き写真の値打ちは今よりずっと高かったのだ。
2011年の東日本大震災では、津波にさらわれた写真を復元するボランティア活動が広がった。被災者は、さぞうれしかっただろう。失いかけた写真は、家庭が営まれた記録であり、家族が生きた証でもあった。とくに、その家族が帰らぬ人となっていたならば……。
アルバムは特別な存在なのだ。かつて「岸辺のアルバム」(脚本・山田太一、TBS系列、1977年)というテレビドラマが人々の心をとらえたのも、家族の結びつきの危うさを、家屋が流されれば消えてしまうアルバムのはかなさに重ねあわせたからだろう。
と、ここまで書いてきて、自身のことを顧みるとゾッとする。私の家は幸いにも震災にも火災にも水害にも遭っていないが、幼少期のアルバムをどこに仕舞っているかがわからない。ただ、ずぼらなのだ。探そうとは思うが、もう散逸しているかもしれない。
色あせた写真には二つの意義がある。一つは、自分自身の記録という側面だ。家族でこんなところへ旅した、親戚にはこんなおじさんやおばさんがいた……というようなことだ。もう一つは、時代の記憶。あのころはこんな服が流行っていた、町にはこんな乗りものが走っていた……といったことである。「私」と「公」の過去を「こんな」だったね、と実感させてくれるわけだ。アルバムには、そんないくつもの「こんな」が詰め込まれている。
「私」についていえば、アルバムの代替品を見つけるのは難しい。だが、「公」は違う。世相をとらえることに長けた写真家が一人いれば、その作品群を通じて「あのころ」の「こんな」を蘇らせることができる。で、私は最近、そんな作品集に出あった。
書名は『東京懐かし写真帖』(秋山武雄著、読売新聞都内版編集室編、中公新書ラクレ、2019年刊)。著者は1937年生まれの写真家。東京・浅草橋で家業の洋食店を営みながら、仕事の合間に東京都内、とりわけ下町の風景やそこに生きる人々の姿を撮ってきた。まえがきによると、「カメラを始めたのは15歳」で「撮り溜めたネガは数万枚」に及ぶ。「写真と洋食屋のどちらが趣味でどちらが本業なのか、分からないくらい」なのだ。
編者名からもわかるように、この本は読売新聞の連載をもとにしている。都内版の一つ、「都民版」に週1回のペースで載ったものから、2011~2018年の72本を選んだという。読売新聞記者のあとがきによれば、担当記者は毎週、秋山さんの洋食店に足を運ぶ。写真1枚1枚について、じっくり話を聞くためだ。そして「『一本指打法』でしかキーボードをたたけない秋山さんに代わり記事を書く」。だから本文からは、語りの口調が感じとれる。
その文章には、秋山さんの被写体に対する思いがあふれている。ただ、この本の主役は、あくまでも写真だ。1編に2枚ほど載せているから全部で百数十枚。ただ、写真は文章のように、これはという言葉を引用できない。当欄では何をどう書こうか。さあ、困った。
ふと思いついたのは、ここにある写真を私本位の視点で味わってみる、ということだ。秋山さんが写真を始めたのが1952年だとすれば、それは私が生まれた翌年だ。実際、作品の撮影年は、多くが私の幼年期から少年期、青年期に重なっている。「公」の記憶ということなら、この本は「アルバム」の役目を果たしてくれるのだ。だから当欄では、作品群を自分の写真のように眺め、あのころは「こんな」だった、と懐旧に耽ることにしよう。
最初にニヤッとしたのは、「羽根をさがす子供」(1957年)だ。男の子たちが路地裏でバドミントンをしていたら、羽根が板塀を越え、道沿いの家の庭に飛び込んだ。一人は、身をかがめた友だちの背中に乗り、背伸びして塀の向こうを見下ろしている。ほかの子たちも、しゃがみ込んで板の隙間から庭を覗いている。そういえばあのころ、ゴムまりの野球で塀越えのファウルを飛ばし、「ボール、とらせてください」と大声を出すことがよくあった。
子どもたちが遊ぶ写真には、ローラースケート(1957年)、ベーゴマ(1966年)、馬跳び(1974年)、相撲(1980年)、縁台将棋(1983年)などがある。どれも路上の光景だ。道の真ん中で、女の子が馬をぴょんと跳び越えている。路面に、ひしゃげた土俵が白線で描かれている。あのころ、私たちは「道路で遊ぶな」と注意されても言うことを聞かなかった。今は車が通らない路地裏でも、子どもたちの遊び声がほとんど聞かれない。
男の子が独り、ハーモニカを吹いている写真もある(1957年)。格子縞のジャンパーの胸元から、猫の顔がのぞいている。愛猫をすっぽりくるんで暖めているのか、それとも、愛猫の体温で自分が暖まりたいのか。寒い季節であることだけは確かだ。それなのに、その子は戸外にいる。気になるのは、背後に見える波板らしき物体だ。あのころは、ありあわせの材木やトタン板で即製した建物があちこちにあった。これも、そんな物置小屋ではないか。
夕暮れどき、子どもたちが連れだって家路の途上にある写真も2枚載っている。どちらも橋の上。片方の写真(1965年)では、向こう岸に工場の煙突が並び、煙がもくもくと上がっている。もう一方(1959年)は、男の子と女の子が総勢7人。はだしの子は靴を手にぶら下げている。「工事現場の水たまりで、泥だらけになって遊んでいたんだ」と秋山さん。あのころ「水たまり」は、それだけで子どもたちの遊びを成立させた。
道路を生活の場にしていたのは、子どもだけではない。大人も、それをただの通り道とは考えていなかった。「嫁入りの日」(1964年)では、花嫁が仲人に導かれ、商店街をしずしずと歩いている。婚礼となれば、新婦が白無垢角隠しの晴れ姿をご近所に見せて回ったのだ。一行を見守っているのは、割烹着姿の女性や子どもたち。通りの華やいだ声を聞きつけて、家から飛び出してきたのだろう。道路が一世一代の大舞台になっている。
「ご近所さん」(1987年)は、近くの住人十数人が路地の道幅いっぱいに並んでいる文字通りの記念写真。食事会の折に撮ったものだという。「こうして勢ぞろいした姿を見ると、お互いの家族を見守りながら暮らしていたんだなと、しみじみ思うよ」。路地は、向こう三軒両隣の私生活をそれとなくつなげる空間だった。それを窮屈と感じるのが今の私たちだが、「見守りながら暮らしていた」と思うゆとりがあのころにはあった。
道路は商いの場にもなった。「部品売り」(1957年)という写真では、露天商が橋のたもとに中古自転車の部品を並べている。よく見ると、値札がついているのはタイヤが多い。「壊れた自転車を安く仕入れて、使える部品だけ抜き取ったんだろうね」。おもしろいのは「橋の上では、硬くなった大福を温め直して売っている人もいたよ」という話。戦後の空気が残っていたあのころ、大人たちはなんでも売りものにして、どこでも店を開いたのだ。
道路の写真をもう1枚。「無理が通れば」(1965年)では、大型トラックが2台、狭い道をギリギリすれ違っている。「今なら立派な物損事故だね」とあるが、この写真ではそうとは断定できない。ただ、秋山さんの証言は含蓄に富む。「運転手がどうしたかって。お互いにそのまま目的地へと走り去っていったよ」――あのころ、運転手の最優先事項はものを運ぶことであり、武骨な車体にかすり傷がついたかどうかは二の次だったように思う。
写真は嘘をつかない。この本では、私が子どもだったころの社会の実相が露呈している。あのころの大人は、法律よりも融通を優先させていたのではないか。だから、道路という公空間で互いに折りあいをつけていた。子どもが道路にいても、近隣の緩いつながりのなかで見守っていた。それがすべて良かったとは言わない。法律や決まりごとは当然、尊重されるべきだ。ただ同時に、あのころにあって今は失われた美風も忘れたくはない。
(執筆撮影・尾関章)
=2021年9月3日公開、通算590回
■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。
■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。
■公開後の更新は最小限にとどめます。
-scaled-1.jpg)