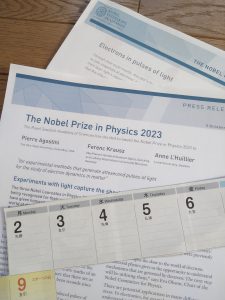今週の書物/
『すごい物理学講義』
カルロ・ロヴェッリ著、竹内薫監訳、栗原俊秀訳、河出文庫、2019年刊
 当欄は、1冊の本を2週にまたがってとりあげることが多くなった。当初は1週1冊を標榜していたが、そんなふうにして数を稼ぐことがばかばかしく思えてきたのだ。たまには2週1冊でいい。いや、ときには3週1冊でも4週1冊でもよいではないか。
当欄は、1冊の本を2週にまたがってとりあげることが多くなった。当初は1週1冊を標榜していたが、そんなふうにして数を稼ぐことがばかばかしく思えてきたのだ。たまには2週1冊でいい。いや、ときには3週1冊でも4週1冊でもよいではないか。
ということで、今週もまた、『すごい物理学講義』(カルロ・ロヴェッリ著、竹内薫監訳、栗原俊秀訳、河出文庫、2019年刊)を続ける。1冊の本にこんなに長居するのも、著者が語るループ量子重力理論にとことん迫り、その世界像を見届けたいからだ。
先々週の話をざっくり言えば、こんなふうだった――。物理世界は「粒」の性格を帯びている。大きさには最小単位があり、それより小分けにできない。その極微世界は幾何学的であり、どのような曲がり方をしているかは方程式で確率的にはじき出される。(*1)
先週は、物理世界の「粒」のありように迫った。それは箱に詰め込まれたボールのようなイメージで、隣りあう粒との間にリンクが張られている。ネットワーク的な世界像といえよう。粒から粒へリンクを伝ってひと回りすると、空間の曲がりが見えてくる。(*2)
ループ量子重力理論の空間にはもう一つ、押さえておきたい特徴がある。「事物を内包する無定形の容れ物」とみてはいけないということだ。空間の量子は「自身と隣り合っている量子のなかに在る」。空間は「隣近所との関係性の織物」ととらえるべきなのである。
このように復習してみると、あることに気づく。本書は空間の議論にかまけて、時間をほったらかしにしてはいないかということだ。実は著者も、そのことを気にしていたらしい。本書の半ば、第7章「時間は存在しない」の書きだしでは、前章まで時間を論じようとしなかったことを率直に認めている。ただ、現代物理学は時間と空間をひとくくりに「時空間」とみているのだから、「そろそろ、見取り図のなかに時間を呼び戻す」と宣言する。
こんな正直な告白もある。量子重力の研究者は「時間と向き合うための勇気が湧くまで」「空間の問題にばかり取り組んできた」。時間の解明は、本書執筆時点の15年ほど前から進展したという。研究者にとっても近年になってからの関心事なのか。
さて、ではループ量子重力理論の時間像は、どんなものか。当欄が繰り返し書いてきたように、ループ量子重力理論の礎となったホイーラー=ド・ウィット方程式には時間変数“t”がない(*1、*3)。それが何を意味するかが、本書を読み進むとわかってくる。
そこではまず、ガリレオ・ガリレイがピサの大聖堂で天井の燭台を見ていて振り子の等時性に気づいた、という話が出てくる。実話かどうかは疑わしいようだが、「伝承」によれば、ガリレオは燭台がゆらゆら揺れる周期を自分の脈拍で測った、とされている。その結果、振り子の周期が振幅によらず変わらないことに気づいたというのだ。著者は、ここで問題を提起する。ガリレオは何を根拠に「脈の打つ時間が一定」と確信したのか。
これには裏返しの話がある。ガリレオの発見後、医師は患者の脈を測るときに振り子を時計として使うようになったらしいのだ。「振り子の振動が規則的であること」を脈で確かめ、「脈が規則的であること」を振り子で確認する――そんなことを私たちはしている。
著者は言う。振り子の観察でも脈拍の測定でも、人は「『時間そのもの』を測っているわけではない」。複数の物理量を測って「ある変量と別の変量を比較している」だけだ。ところが物理学はこれまで、時間変数“t”の存在を「仮定」してきた。この慣習を断つのが量子重力理論だ。物理量A、B、Cがあるとすれば、それらを“t”の関数A(t)、B(t)、C(t)ではなく、変数相互の関数A(B)、B(C)、C(A)のように考えようとする。
この視点に立てば、世界の変化は事物間の関係の変わり方ということになり、世界が「時間のなかで変化する」ことはない。これは、空間を「容れ物」ではなく「隣近所との関係性の織物」ととらえるのに似た考え方だ。時間もまた「容れ物」ではないらしい。
さて、ここから先は難解だ。当欄は、本書が提示するイメージに頼って話を進めるしかない。著者は、物理現象を「箱」で説明する。ビリヤードの球2個がぶつかって二つの方向へ転がっていく現象を例に挙げ、その舞台となる時空間を箱で表す。本書掲載の略図では、箱が直方体で、その一辺が時間軸のように見えるが、単純にそう理解してはいけないことが文章を読むとわかる。なぜなら、「箱自体が時空間を『含みこんでいる』」からだ。
箱には別の表現もあって、そちらのほうがピンとくる。それは「軟体動物」の小片に似ており、「鮨(すし)のような形」をしているというのだ。余談だが、著者が「軟体動物」をもちだしたのには訳がある。アルバート・アインシュタインが、時空間の曲がりである重力場のことを「軟体動物」にたとえているからだ。その比喩を「鮨」にまで飛躍させたのは、日本人読者向けのサービスではあるまい。きっと、ご本人が和食好きなのだ。
問題は、「鮨」のようなものが何かだ。ループ量子重力理論では、ビリヤードの球同士の衝突という物理過程を考えるとき、球そのものだけでなく、時空間など「球を取り巻くすべてのもの」を考えに入れなくてはならない。「鮨」は、これらすべてを含んでいる。
本書によると、ここで目を向けるべきは「鮨」の末端だ。両端のうち片方は物理過程の始まりに、もう一方は終わりに相当する。ループ量子重力理論の方程式は、過程の始まりと終わりのそれぞれがとりうる「すべての状態の確率」をはじき出してくれるというのだ。ここでビリヤードに話を戻すと、これによって私たちは、衝突する球がどのように「鮨」に入り、どのように「鮨」から出ていくか、ということを確率的に知ることができる。
では、末端と末端の間はどうなのか。ここで助けになるのが量子力学の世界像だ。一つは、ウェルナー・ハイゼンベルクの行列力学。「量子力学は、過程の最中になにが起こるかは教えてくれない」とする。もう一つは、リチャード・ファインマンの「経路総和」。粒子の動きをいくつもの経路の束とみる。この考え方に立てば、二つの末端の間には、粒子がとりうるすべての経路を含み、ありうるすべての時空間をはらむ「雲」が存在する。
ループ量子情報理論は空間を「網」とみる。それが、時空間では「鮨」の末端に現れるという。ここで「網を手にもち、それを動かす」行為を思い描こう。それによって「網」の結び目である「節」は点が線となり、「節」と「節」のつながり(「リンク」)は線が面となる。著者は、これを「網の歴史」「網の歩み」と呼び、そこに生まれる構造を「泡」に見立てる。時空間の「雲」は「生じうるすべて」の「泡」の重なり合いとみてよいらしい。
本書によれば、物理学者はこの「泡」によって特定の物理過程の確率を算出する。ここで必要なのは、同じ一つの末端を分かちあう「泡」をすべて足し合わせて、その「総和」を求めることだ。ループ重力量子理論の方程式は、この計算を可能にしてくれる。
本書が描く時間を要約すれば、こうなる。世界には、事象に先だって「容れ物」の役目を果たす時間も空間もない。空間は「節」と「リンク」でかたちづくられる関係性の「網」であり、「網」の状態が変わることで「時空間」が生じる、というのだ。
ではなぜ、私たちは時間を一様の流れのように感じるのか。本書には「空間と時間は、大きなスケールにおいてはじめて現われる、近似的な存在」という示唆がある。「大きなスケール」には、時の流れを実感させるしくみがあるようだ。そのことは著者が別の著作で詳述しており、当欄もすでに紹介した(*4)。本書終盤にもヒントとなる章があるが、とりあえず今回のシリーズは3回で中締めにする。機会をみて再開しよう。
いま言えるのは、時間を絶対視するのはもうやめようということだ。時間は事象の相対的な変化のなかにある。そう思うと、1日という時間がちょっと長くなった気分になる。
*1 当欄2023年10月20日付「ロヴェッリの物理、空間は粒」
*2 当欄2023年10月27日付「ロヴェッリの物理、空間は網」
*3 当欄2023年5月5日付「『時間がない』と物理学者は言った」
*4 当欄2023年5月12日付「時間の流れを感じる物理学」
(執筆撮影・尾関章)
=2023年11月3日公開、通算702回
■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。
■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。
■公開後の更新は最小限にとどめます。
-scaled-1.jpg)