今週の書物/
『ごった煮のおもしろさ「熊野山略記」を読む』
桐村英一郎著、はる書房、2021年刊
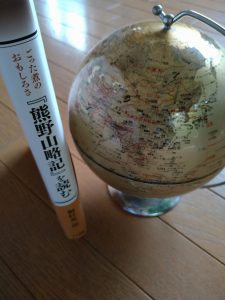
熊野とは、不思議な縁がある。
一度目は、火の玉を追いかけたときだ。1985年10月8日、謎の火の玉が列島の夜空を横切った。甲子園球場では観衆が総立ちになったから、覚えている方もおられるだろう。そのころ、私は朝日新聞大阪本社の科学記者だった。「どこに落ちたか、見てきてくれないか」。科学部の上司は、若手部員の私に無理難題を押しつけた。社が用意したタクシーに社会部の2人と乗り込んで、一路、火の玉が消えた方角へ針路をとった。
社を出発する時点でわかっていたのは、火の玉が南のほうへ流れたというくらいだ。落下場所など見当もつかなかった。携帯電話が広まっていない時代なので大きな携帯無線機を持たされた記憶があるが、本社は追加の指示をなにも言ってこない。大阪の南には紀伊半島が控えているだけだ。だったら、その突端をめざすよりほかないではないか。こうして私たちの車は南紀に入り、熊野の森の闇をさまようように走りまわったのである。
当然、これは無駄足だった。翌日に帰阪後、南紀で隕石の破片らしいものが見つかったというニュースが現地から届いたが、それが火の玉の残骸だとは断言できなかった。今では、あの火の玉は隕石でなく、人工天体の落下だったという説が有力のようだ。
次に熊野の森に入ったのは、さほど昔ではない。熊野古道見たさで思い立った私的な旅行だった。那智の滝を眺め、熊野本宮大社に参り、中辺路(なかへち)を歩き、童子の像などを見て回った。あいにくの土砂降りで、全身ずぶ濡れになったことを覚えている。
深い闇と激しい雨。これが、私の皮膚感覚に刻まれた熊野だ。ただ考えようによっては、熊野は私に素顔を見せてくれたのだとも言える。ここは〈ふつうの日本〉ではない、そのことを肝に銘じよ、とでも戒めるように。それでいて、熊野は心地よくもある。〈ふつうの日本〉からふらりとやって来ても拒まれることはない。これは、私が新聞社にいたころ、南紀に幾度となく出張した折に町の人々の表情から感じとったことである。
で、今週の1冊は『ごった煮のおもしろさ「熊野山略記」を読む』(桐村英一郎著、はる書房、2021年刊)。著者は、1944年生まれの朝日新聞元記者。ロンドン駐在、大阪、東京両本社の経済部長、論説副主幹を務めた。経済畑、科学畑と専門分野は異なるが、私にとっては大先輩である。2004年に定年退職すると奈良県明日香村に住み、神戸大学で客員教授を務めた。現在は、三重県熊野市在住。古代史探究に打ち込み、著書も多い。
著書の一つに『熊野からケルトの島へ――アイルランド・スコットランド』(三弥井書店、2016年刊)がある。この本は、当欄の前身「本読み by chance」で紹介した(2018年5月4日付「熊野とケルト、島の果ての奥深い懐」)。ユーラシア大陸から見れば、東西の辺境のそのまた辺境といえる場所に光を当て、両者に通じあうものを浮かびあがらせた。その着想は、国際経済記者の職歴と定年後の知的関心が化学反応したもののように思える。
その著者の最新作が、この『…「熊野山略記」を読む』である。ご本人から送っていただいたので、ぱらぱらめくると漢字が多い。漢文がそのまま載っているページもある。高校時代の授業が思いだされる。これは困った、とても読み通せないな、と白旗を揚げた。
本書は、著者が「熊野山略記」(以下、「略記」)という古文書を読み込んで、熊野文化の起源を探ったものだ。「略記」は室町中期以前の作とみられ、「本宮・新宮・那智山から成る熊野三山の由来、聖地たる理由」などを三巻にまとめている。この『…「熊野山略記」を読む』は三部構成。第三部は「略記」原文、第二部はその漢文を日本文に読み下して解説したもの。著者は、第一部で「略記」を踏まえた自身の熊野観を披歴している。
そうか、と私は思った。第三部はもちろん、第二部も私には手に負えない。だったら、第一部だけを読もうではないか。第二部の読み下しと解説は著者が成し遂げた偉業だが、だからこそ準備不足の私にあれこれ言う資格はない――そんなふうに都合よく考えたのである。
第一部は「主人公の諸相」と題されている。ここで著者は、「略記」に登場する主な人物、神仏のあれこれを物語風に紹介する。一読してわかるのは、人物や神仏の国際性だ。飛行機もインターネットもない時代に、よく世界をこれだけ広くとらえられたものだと思う。
たとえば、熊野権現。熊野三山に祀られる神は、仏や菩薩の化身なので権現と呼ばれる。この神は「唐からはるばる飛来」したのだという。「飛来」だから、海路ではなく空路だ。唐の天台山(中国浙江省)→九州の英彦山(福岡大分県境)→四国の石鎚山→淡路島の諭鶴羽山とトランジットを繰り返し、南紀に到着。熊野に着いても、あちらの梢、こちらの峰と小飛行している。熊野人の想像力には、ほとんど今の航空便と同じ自由度があったのだ。
「略記」が「おおらか」なのは、別の箇所では異説を平気で載せていることだ。それによると、熊野権現の「飛来元」が、唐ではなく天竺(古代インド)の摩訶陁国(まがだこく)だという。東アジアにとどまらず、南アジアまで視野に入れているのである。
「略記」には、上記2説を折衷させた筋書きも出てくる。後に熊野権現となる慈悲大顕王が天竺の迦毘羅国を旅立ち、唐の天台山を経て、九州→四国→淡路島→紀伊国のルートをたどったというのだ。ちなみに、迦毘羅国は釈迦が生まれたとされる国である。
権現だけではない。那智山の青岸渡寺を開いた裸形上人も、もともとは海外の人らしい。「略記」によれば、「熊野川河口の地で長年修行を重ねた後に那智に移った」ことになっている。では、どこからその河口部にやって来たのか。著者は、この人がインド・ジャイナ教「裸行派」出身の行者だとする説や、「仁徳帝の時代、印度より一行六人と共に熊野浦に漂着」という青岸渡寺に伝わる説を紹介する。こちらは海路の来日だ。
熊野のある紀伊半島は、海を挟んで世界とひと続きだったと言ってよい。「略記」には、「南蛮」(エビス、「夷」「狄」「戎」「江賓主」とも書く)も登場する。「黒潮に乗って南方から来て、熊野灘沿岸に住み着いた『海の民』」だ。「南蛮」は敵役となり、征伐される側に回るのだが、その子孫たちが地元に根を張って「繁昌」して「氏人」になったという話も織り込まれている。著者はそこに、「熊野のおおらかさと懐の深さ」をみる。
さらに驚かされるのは、その南蛮制圧に寄与した「熊野三党」のルーツだ。「三党」は、榎本氏、宇井氏、鈴木氏を名乗る平安初期の豪族だ。「略記」では、それぞれの家系をさかのぼると天竺に行き着くという話が綴られている。天竺の慈悲大顕王、即ち、後の熊野権現は来日に先立って家臣を日本列島へ送り込んでいた。その子孫たちが熊野の豪族として根づいた、というのだ。著者があきれるように、「略記」で「一番突飛」な話ではある。
この話が本当なら、すごいことだ。1200年ほど昔、日本列島を舞台に海外にルーツをもつ二派が相争ったことになる。片や「南蛮」、こなた「天竺」。両者が交差した場が熊野というわけだ。その展開は、純血主義志向の歴史観からは大きく外れている。
もちろん、これは伝説半分の、眉に唾をつけて聞くべき物語だ。ただ、たとえ眉唾ではあっても、それが日本の政治中心からさほど遠くない一角に史話として生き延びてきたという事実は、心にとめるべきだろう。そのことは、私が熊野の闇で、あるいは熊野の森で、ここは〈ふつうの日本〉とは違うのだ、と囁かれたように感じた記憶と響きあう。と同時に、来訪者を拒まない気風が心地よかったという体験を思い起こさせる。
著者はあとがきで、「熊野の地が私を『ほっとさせる』のは、本音や混沌(坩堝のような入り混じり)をあえて隠したり、避けようとしたりしない、その有り様に惹かれるからだ」と打ち明けている。そんな空気を日々吸い込んでいる先輩を、私はうらやましく思う。
*本文にあるルビは原則として省いた。
(執筆撮影・尾関章)
=2021年7月16日公開、通算583回
■引用はことわりがない限り、冒頭に掲げた書物からのものです。
■本文の時制や人物の年齢、肩書などは公開時点のものとします。
■公開後の更新は最小限にとどめます。
-scaled-1.jpg)



